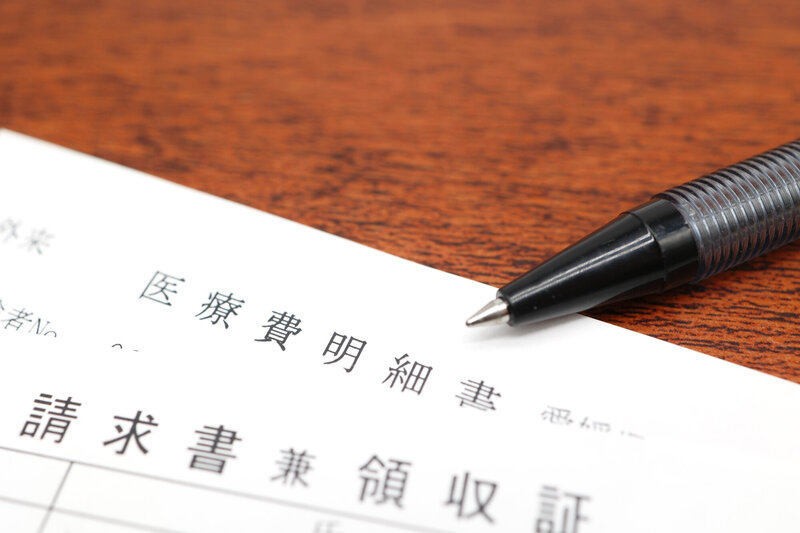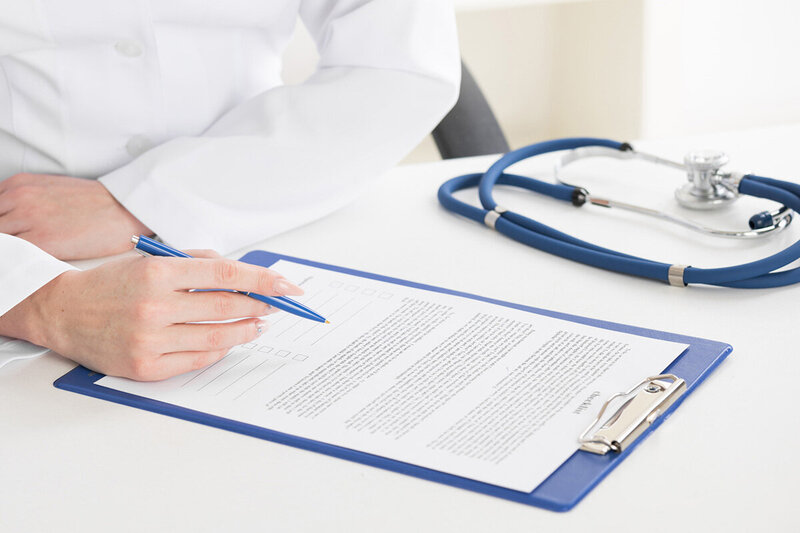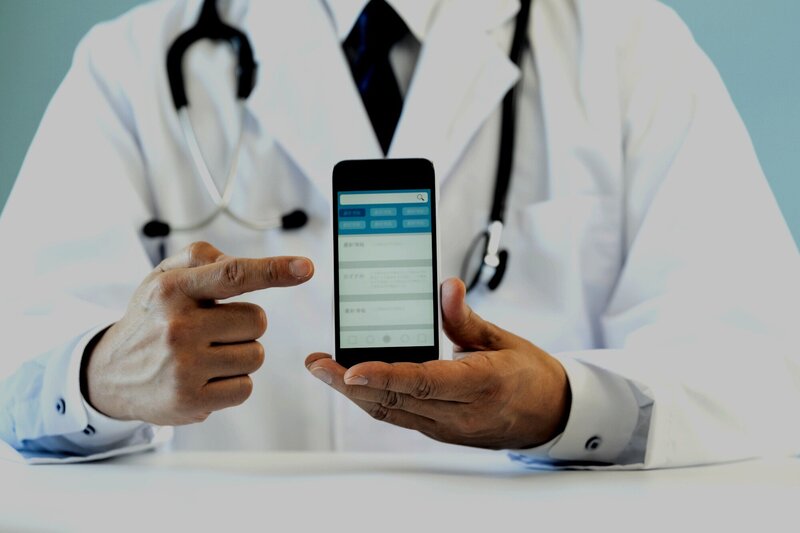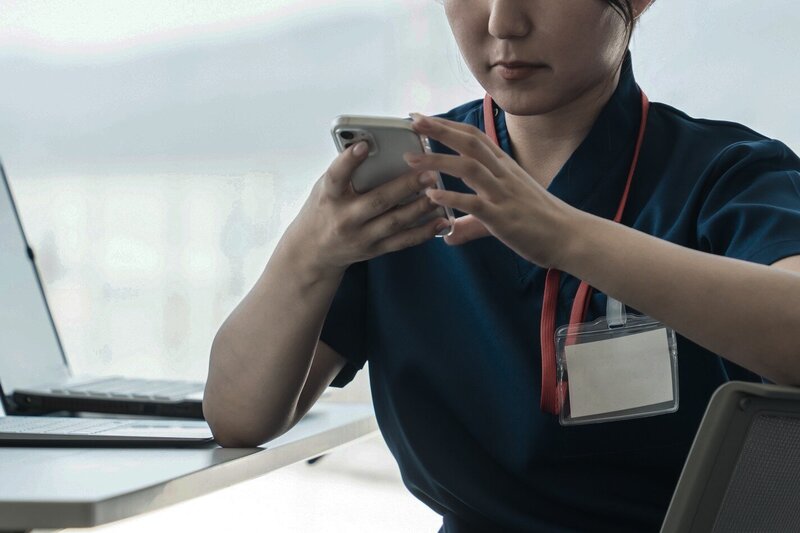お気軽にご相談ください!
クリニック開業お役立ちコラム
勤務医から開業医への「モードチェンジ」を成功させるポイント【現役開業医がアドバイス】

専門性を追求する大学病院、あるいは地域の基幹病院の勤務医と、クリニックの開業医には、求められるサービスや診療の内容に大きな違いがあります。クリニックの開業を大病院の勤務医が目指す場合、どのような視点でキャリアを積めばいいのでしょうか。大学病院の医師から開業医に転身した著者が、具体的に解説します。
勤務医と開業医では「理想のキャリアプラン」は大きく異なる
医師の理想的なキャリアプラン・キャリアパスは、最終ゴールが勤務医なのか、それとも地域医療を展開していく開業医なのか、目指す着地点の選択によって大幅に変わります。
開業医を目指すなら、これまでの自分の臨床経験を俯瞰し、強さ・弱さを明確にしたうえで、勤務医であるうちにさまざまな現場での医療経験を積む必要があります。なぜなら、開業後は、労務・人事・医師会業務など、医業とはまったく質が異なるマネージメント業務に時間を割かれ、診療技術を学ぶ時間が圧倒的に減少するからです。
また、病院勤務の間でも、レセプトや患者負担、薬局との連携など、医業以外のスタッフとも懇意にしていくコミュニケーション能力をつけておく必要があります。
患者様に不人気=開業しても、金銭的な困窮の可能性

勤務医は、近年では「上げ膳・据え膳」の状態にあり、勤務するスタッフの家庭の事情や金銭感覚、物事の考え方などが大きく異なります。そのため、雑談ベースで話をして、実情を把握しておくことが重要です。
筆者の場合も、最後に基幹病院で勤務医をしていたときには、事務長をはじめとする医事課・薬剤部・臨床検査科とも懇意にしており、退職する前年には、病院職員の組合代表候補に選出されるレベルにまで認知度・貢献度とも高かったと自負しています。これらも「開業して社会貢献への道を開拓できる」という自信・実績につながりました。
なぜかというと、開業医になると、地域社会で個人などから支持されない、つまり患者様に不人気であると、金銭的な困窮に直結するからです。
クリニックの不人気の主たる理由は、院長の診療態度やコミュニケーション能力・人柄など、医業とは関係のない要素が多分にあります。そのため、勤務医時代からこれらを意識して、積極的に日々のコミュニケーションを図ることが重要です。
病院の他職種の方々に信任を得る以外には、診療科の部長や医長をしていた、雇われ院長をしていた...など、リーダーとしての経験も開業に有利だといえます。
なぜなら、クリニックは小さな組織から次第に拡大していきます。そのなかで、スタッフ管理、日計表・月計表などの資金管理、業務遂行のためのシステム構築、診療報酬の請求の原則などの業務について、院長がすべて対応する必要があります。これらのさまざまな業務について、ひとつひとつ対応していく力には、リーダーとして業務を取りまとめた経験が活きてくるからなのです。
当然、医師としての能力は必要ですが、そのうえで、診療報酬や公費・自費の医療・労務管理・経営に関する知識も求められます。さらに、地域社会は、地域の薬局・訪問診療ステーション・市域包括支援センター・幼稚園や保育園・福祉施設などの多職種連携で成立しているため、そこにうまく溶け込めるコミュニケーション能力も必要となるのです。
「さまざまな場所での勤務経験+マーケティング能力」が組織運営の力に

現在は、医療スタッフの確保が困難であり、院長にある程度の経験やビジョンがなければ、スタッフは容易に退職していくという厳しい時代です。
開業前、大きな医療機関(大学病院や地域の基幹病院)に勤めていたなら、病院自体のネームバリューによって自然と患者が集まってきていたでしょう。
しかし、開業後は、自分自身でSNSやホームページ、その他の広告媒体を通じてクリニックや自分の存在を認知してもらうことが必要となりますし、受診していただいた患者様を大切にし、再診を促しながらも他家族や友人などにクリニックを勧めてもらう仕組み作り、マーケティングの能力も重要になってきます。
このようなマーケティング能力は、学会や研究会・勉強会などの臨床・研究での運営や幹事や、自分の趣味であっても集客などの経験があれば、形を変えて集患スキームの構築にも活きてくるため、積極的に規模を問わず組織を運営する、という経験も重要となります。
また、開業する前には、多数のクリニックでの勤務を経験することも、開業する際に役立ってきます。勤務医であるうちに、自分が目指すべきクリニックの理想像に近く、幅広い診療内容を展開して患者数も多い、盛業しているクリニックに、積極的に定期非常勤やスポット勤務で幅広く経験を重ねることをお勧めします。
個人のクリニックや小規模の医療機関であるほど、経営に対してはシビアな目を向けることになります。盛業しているクリニックでの施設基準や診療報酬の算定、スタッフの動きなどを体験していくことは、その後の開業のコンセプトや、それぞれのクリニックの良し悪しの経験値・モデルとなり、自分がめざす開業のスタイルやイメージ作りに大きく役に立ちます。
「自分はクリニックを開院してどのようになりたいのか」を考える
筆者自身も、基幹病院時代は小児科の所属でしたが、0歳から100歳まで診療を広く展開している山奥の病院にスポット勤務へ行きました。
院長はもちろん、さまざまな科の先生、スタッフ、なにより患者様とご家族に「彼は家庭医を目指している」と認知され、多くの業種に便宜を図っていただいたことも、今の自分の基礎となっています。

このほか、どの診療科においても、心療内科的な要素を抱えた患者様が一定の割合で存在しています。筆者も内科・小児科・アレルギー科を標榜していますが、約1割程度の患者様は心療内科・児童精神科的な要素があり、程度の差はあるものの、対応を要することがあります。こうした患者様に対してファーストタッチをおこなう際に、開業医としてのスキルを問われます。
また職員のメンタル管理、とくに業務に関連した人間関係の適応障害・抑うつ性エピソードなどには、管理者としての労務管理や精神的な配慮が必要です。メンタルが不調な人に対応する経験をビジネス・プライベート問わずに持つことも、円滑な組織運営や集患という観点から大いに役立つといえます。
とはいえ、どのような経験を重ねたうえで開業するのか、ということは、まずは、自分はクリニックを開院してどのようになりたいのか、哲学的な問いに明確に答えられるような、その理由を裏打ちできるエピソードをいくつか持つことが始まりです。
そして不退転の気持ちと、強いモチベーションをもって、勤務医のうちにさまざまな経験を積むことで、開業のコンセプトや、準備計画に具体的なアイデアが多く出てくるようになります。
普段の勤務ではコミュニケーション能力や人柄を意識し、金銭感覚などの経済・法律・マーケティングという医業と直結しない事に積極的に関わり、閉鎖的な大病院の外の世界を体験することが、究極のモードチェンジだといえるでしょう。
株式会社TTコンサルティング
医師 武井 智昭
監修者
株式会社コスモス薬品
本社を福岡県福岡市に置く東証プライム市場上場。
「ドラッグストアコスモス」の屋号で、九州を中心にドラッグストアチェーンを展開。
2024年5月期決算売上高は9,649億8,900万円。
M&Aを一切行わず、33年連続増収。
日本版顧客満足度指数の「ドラッグストア」において14年連続第1位を獲得。
クリニックの開業サポートにも注力し、2024年8月現在、開業物件店舗数は約350店舗。 集患に有利なドラッグストア併設型物件を全国各地で多数取り扱っている。

弊社が開業支援をさせていただきます
コスモス薬品が運営するドラッグストアは、日常生活に必要なものが何でも揃う生活の拠点となるお店。その地域で便利に安心して暮すために欠かせない、電気や水道のような社会インフラであるお店。
そこに専門性が高いクリニックが加われば、さらに「豊かな生活」を提供することができます。
コスモス薬品は、地域医療の担い手である開業医を全力でサポートしてまいります。