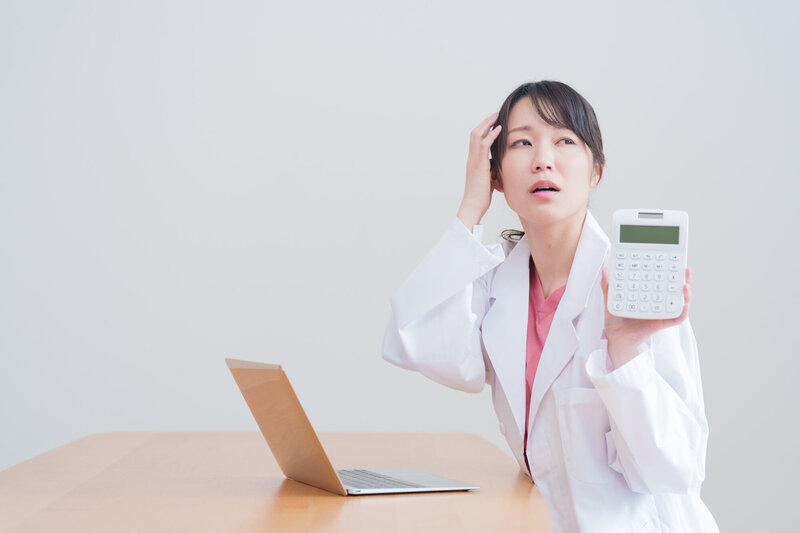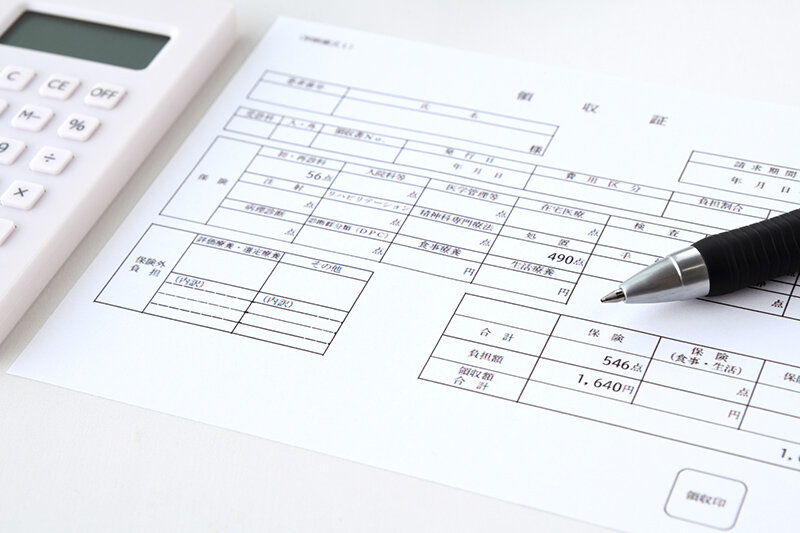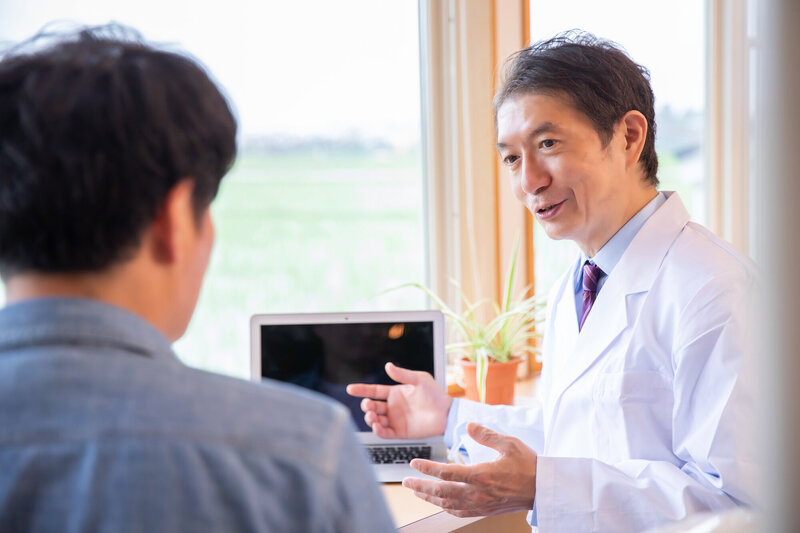お気軽にご相談ください!
クリニック開業お役立ちコラム
医療法人内に貯まったお金...院長の手元に戻す方法はあるか?【会社設立・海外活用にくわしい弁護士が解説】
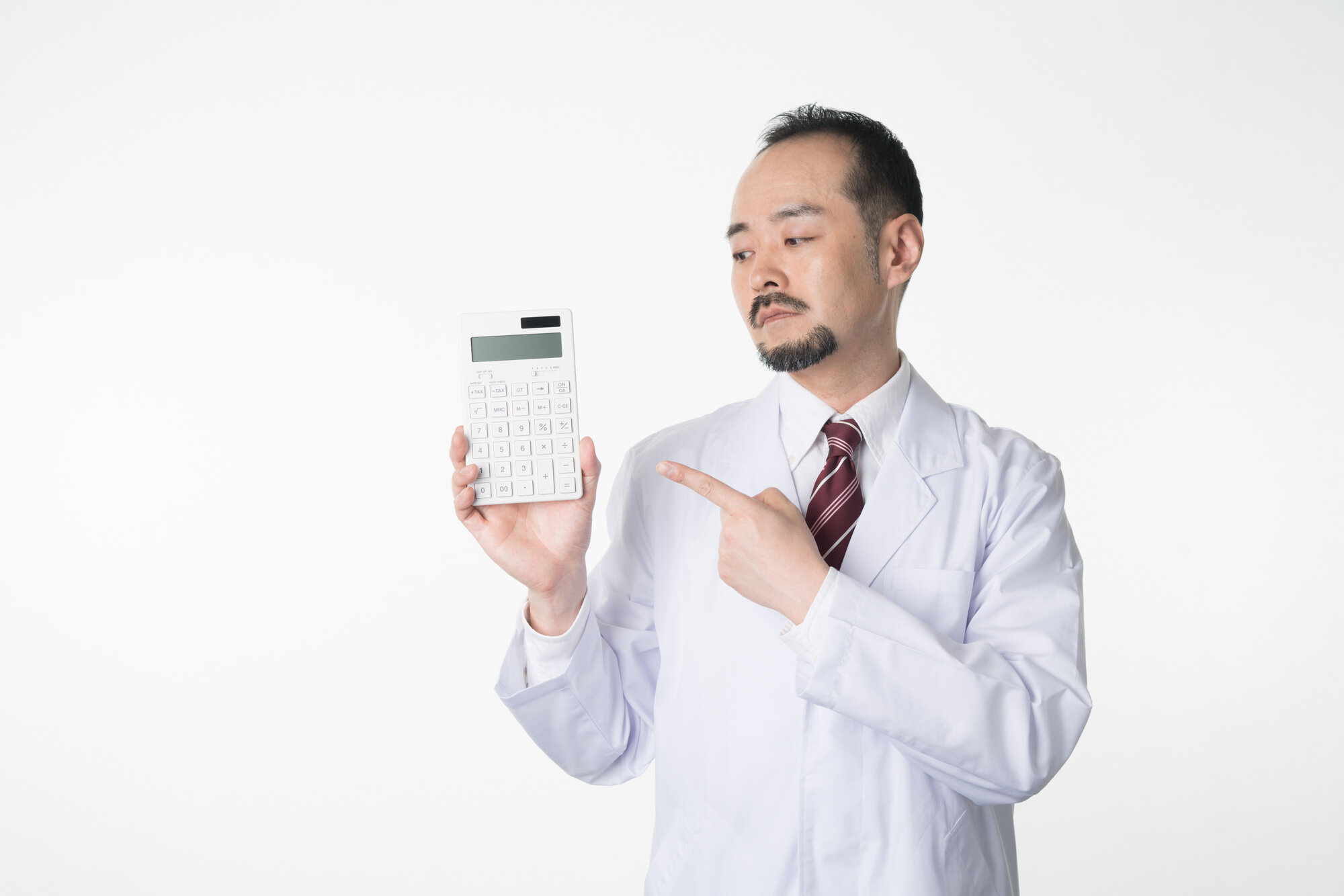
経営するクリニックがある程度の規模になると、医療法人化を検討することになります。しかし、医療法人の儲けは院長個人の資産にはできないため、残念な思いをしているドクターも多いでしょう。しかし、医療法人の仕組みを、同じく法人である「株式会社」の仕組みと比較することで、参考になる点が見えてきます。
株式会社・医療法人...それぞれの特徴と仕組み

まず株式会社の特徴として、
①出資者の責任は出資の限度である
②出資持分(株式)を他者に譲渡できる
という点があります。
株式会社は、もともと大勢が集まって作る仕組みでしたが、いまは出資者1人でも作ることができます。株式会社を100%支配するオーナーであれば、株主(=自分)へ配当をすることで、自分への金銭的メリットをもたらすことも容易です。
医療法人の場合も、株式会社と同じく有限責任とされていますから、もし経営に失敗したとしても、出資を上回る責任を負うことはありません。
一方、譲渡性について見ると少し複雑です。
平成19年(2007年)4月施行の医療法改正までは、医療法人に出資したオーナーは「出資持分」を持っていました。そのため、引退するときに出資持分の払戻しを求めたり、出資持分を譲渡したりすることができました。
しかし、現行法の下で作る医療法人は、「出資持分」がないため、払戻しや出資持分譲渡をすることはできません。そのため、引退する場合なども、医療法人から退職金を受け取る方法しかありません。
さらに、「出資持分」がないことから、オーナーへの配当も認められていません(「出資持分」が無いので「オーナー」という表現も不正確ですが)。
医療法人が「出資持分無し」と法改正されたのは、「医療法人の経営安定化」が目的
現在は「出資持分」なしの社団医療法人しか設立できなくなったわけですが、この改正の目的はどこにあるのでしょうか?
従来、払戻しの額をめぐってトラブルが発生したり、出資者である医師が亡くなって相続が生じたときに相続税が払えないという事態が発生したりしていましたが、これらを防ぐのが、この改正の目的だと説明されています。
さらに、より根本的な目的として「医療法人の経営安定化を図る」という点があげられます。
医療法人の経営安定化のため、行える業務も限られている

上記の「医療法人の経営安定化」という目的は、医療法人の制度の全体にわたって貫かれています。ここでも、株式会社と比較して見ていきましょう。
株式会社の場合、銀行業、証券業などのように、別途ライセンスを取得する必要がある業務もありますが、基本的にはどのような業務も行うことができます。
一方、医療法人の場合、そもそも行うことのできる業務が限定的で、本来業務・附帯業務・付随業務のみであり、それ以外の業務は一切できません。たとえば、余剰資金でビジネスをしたり、株式投資をしたりすることはできないのです。
この「本来業務・附帯業務・付随業務」について簡単に説明すると、本来業務は、病院の運営などです。附帯業務は、保健衛生に関する業務、医療関係者の養成又は再教育、医学又は歯学に関する研究所の設置などの業務で、本来業務に支障のない範囲で行うことができます。付随業務とは、医療機関に隣接する患者用や従業員用の駐車場の経営、院内に設置する売店などの業務であり、本来業務に付随する業務のことです。
医療法人が「付随業務として行える業務」をMS法人に行わせるメリット
このように、病院内の売店などを医療法人が経営することはできるのですが、売店で利益が出たとしても、その利益を「医療法人の外に出す」ことはむずかしいのです。
ならば、売店経営のように医療法人でなくても行える業務については、医療法人が行わないほうがよい、という考えが出てきます。
そうして作られたのが「MS法人」(メディカル・サービス法人)です。
MS法人とは、法律用語ではありません。MS法人は、普通の株式会社などを設立し、病院内の売店、駐車場経営、病院の清掃などを行っています。率直に申し上げると、医療法人に利益が貯まらないよう、できる限りMS法人に利益が移るように利用されています。
海外の医療施設に出資するという裏技
しかし、MS法人を使っても医療法人に利益が貯まってしまい、外に出したいと考えているところもあるでしょう。
そういった医療法人に使いやすそうな規定が、平成26年(2014年)の改正により加えられました。それが、附帯業務として加えられた「海外における医療施設の運営に関する業務」です。

この背景には、日本の医療技術を国際展開させようとしていた経済産業省の働きかけがあったと見られます。
たとえば、この「日本の医療技術・サービスの国際展開支援(アウトバウンド)」というページ(https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/iryou/outbound/index.html)を見ますと、2014年頃から経済産業省が医療技術・サービスの国際展開支援に力を入れていたことがよくわかります。
つまり、医療法を管轄する厚生労働省は、医療法人の内部に資金を貯めてできるだけ外に流出させないよう、医療法を用いて高い壁を作ってきましたが、経済産業省が、医療技術・サービスの国際展開という名目のもとに横穴を開けたといえそうです。
海外の医療施設に出資したあと、自分に資金は戻ってくるか?
医療法人に溜まった資金を海外医療施設に出資しても、その進出先の国で医療施設を運営するだけでは、院長の手元には資金が戻ってきません。
資金を手元に戻す方法はいくつか考えられますが、そのひとつは、進出先の医療施設に自ら勤務するというかたちで報酬を得ることでしょう。
もちろん、医師は国家資格であり、国ごとに資格が定められています。日本で医師免許を持っていても、外国でそのまま使えるわけではありません。
とはいえ、いくつかの国では、日本の医師免許で診察を行える国があります。シンガポール、中国などです。
ただ、一定の条件があります。
シンガポールの場合は人数制限があり、30名までとなっていますから、簡単にその資格を得ることはできません。また、中国の場合、外国人医師免許試験に合格することが要件とされています。
そんななか、非常にハードルが低いのがカンボジアです。登録すればカンボジア国内で診察を行えるのですが、この登録も通常1~3ヵ月で完了します。
そのため、カンボジアに医療施設を設立して出資することにより、「日本の医療法人⇒カンボジアの医療施設⇒自分自身」という余剰資金の還流を比較的容易に行えるといえそうです。
とはいえ、この制度の本来の趣旨にのっとり、日本の医療技術の普及を図り、カンボジアの医療水準の向上に貢献していくという志を忘れてはなりません。
OWL Investments
代表取締役・弁護士
小峰 孝史
監修者
株式会社コスモス薬品
本社を福岡県福岡市に置く東証プライム市場上場。
「ドラッグストアコスモス」の屋号で、九州を中心にドラッグストアチェーンを展開。
2024年5月期決算売上高は9,649億8,900万円。
M&Aを一切行わず、33年連続増収。
日本版顧客満足度指数の「ドラッグストア」において14年連続第1位を獲得。
クリニックの開業サポートにも注力し、2024年8月現在、開業物件店舗数は約350店舗。 集患に有利なドラッグストア併設型物件を全国各地で多数取り扱っている。

弊社が開業支援をさせていただきます
コスモス薬品が運営するドラッグストアは、日常生活に必要なものが何でも揃う生活の拠点となるお店。その地域で便利に安心して暮すために欠かせない、電気や水道のような社会インフラであるお店。
そこに専門性が高いクリニックが加われば、さらに「豊かな生活」を提供することができます。
コスモス薬品は、地域医療の担い手である開業医を全力でサポートしてまいります。